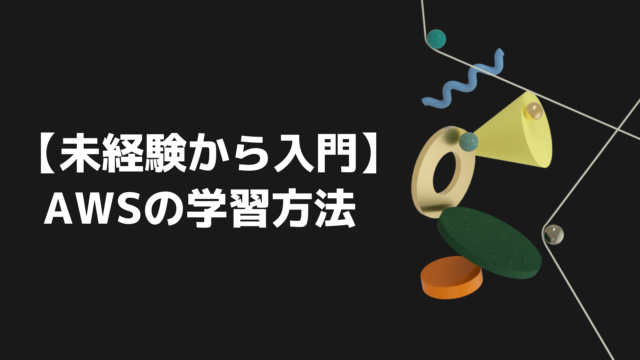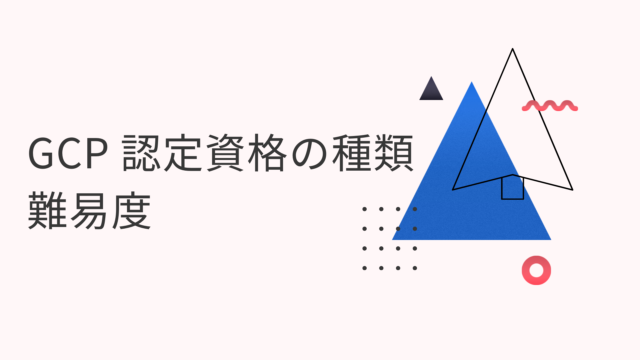この記事では【GCP認定資格 Professional Cloud Network Engineerの勉強】についてご紹介します。
今回は本資格に合格されている現役エンジニアの西野さんに記事を寄稿いただきました!
この記事を書いた人:西野 直也
- 5年間ネットワークエンジニアとして従事
- HR業界でSRE 2年目
- GCP歴は3年目
- ネットワークスペシャリストの資格は取得済み
転職する際に資格という武器が欲しかったので受験しました
GCP認定資格 Professional Cloud Network Engineerとは?
GCP認定資格 Professional Cloud Network Engineerは、「GCPを活用してセキュアなネットワークの構築及びさまざまなシステム要件を適切に満たしたネットワークの検討ができることを証明できる資格」です。
試験範囲としては以下のようなGCPにおけるネットワーク分野の知見が多岐に渡り問われます。
- ネットワークの設計と計画
- 可用性検討
- DNS
- セキュリティ
- 負荷分散
- VPC
- ファイアウォール
- ハイブリッドクラウド/マルチクラウド
- オンプレへの接続
- k8sの利用
- VPCの取り扱い(VPC ネットワーク ピアリング、リーティング、ロードバランサ、共有VPC)
など
【 Professional Cloud Network Engineerの概要 】
試験難易度
難しい
試験時間
2時間で50問
受験方法
オンサイト試験または、オンライン試験
受験費用
200 米ドル
言語
英語
GCP認定資格 Professional Cloud Network Engineerの勉強方法
私が行った「GCP認定資格 Professional Cloud Network Engineerの勉強方法」について紹介していきます。
この勉強法の前提として、私の場合すでに「ネットワークスペシャリスト」という高度情報資格の取得を経てネットワークの基本的な知識を有した状態で本試験に挑んでいます。
そのため、「ネットワーク?なにそれ美味しいの?」という方はまずはネットワークの基本を学ぶ必要があります。
ネットワークを学ぶための教材はたくさんありますが、私が初めてネットワークの担当になった際に最初に渡された方はこちらでした。(名著です。)
さて、基礎的なネットワークの知識を持った状態で進めるべき勉強法についてですが
具体的には以下のような手順で学習を進めていきました。
【 GCP認定資格 Professional Cloud Security Engineerの勉強方法 】
- GCPにおけるネットワークサービスを網羅的に理解する
- 模擬試験をたくさんやる
1. GCPにおけるネットワークサービスを網羅的に理解する
私の場合、GCPは業務で利用していたものの試験ガイドで出てくるようなGCPのサービスを全て触ったことはありませんでした。(特にマルチクラウドとか、ハイブリッドクラウドで使用するようなサービスについての理解は一切ありませんでした。)
私の場合、会社の援助でCourseraが利用できたので、GCPが推奨するトレーニングプログラムを一通りこなしました。
とはいえ、まだ試験ガイドにあるような範囲を網羅できていない気がしていました。
そこで利用したのが以下の【GCP – Google Cloud Professional Cloud Network Engineer】という動画教材です。

2. 模擬試験をたくさんやる
模擬試験は無料で使えるものが結構あったのでそちらを利用していきました。
まじ利用したのがGCPが提供しているこちらの模擬試験です。
これでなんとなく試験形式を理解することができました。
この次に、こちらの海外サイトで演習問題を解きまくりました。
中には「どれが解答なのかわからん!」みたいな問題もありますが、一旦スルーしてます。
上記模擬試験をやっていく中でやはり理解が不足していたサービスや考え方に出くわすこともあるのでその時は定期的にGoogleのホワイトペーパーを参考にしながら学習を進めていきました。
まとめ
今回は【GCP認定資格 Professional Cloud Network Engineerの勉強】についてご紹介しました。
クラウドをベースとしたネットワークエンジニアの需要は年々上がっているので、是非この機会に挑戦してみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました!